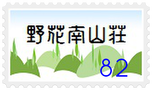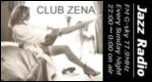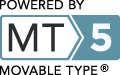クリの葉が巻かれて「揺りかご」(揺籃=ようらん)が作られている。オトシブミの仕業。葉を切って丸め、中に卵を産む。種類によって丸めた葉を地面に切り落とすのもいて、巻かれて落ちた葉が「落とし文」のよう。落とし文とは相手に直接手渡すことができないため、地面に置かれた手紙のこと。封建時代の直訴状であったりラブレターだったりする。なんとも昆虫だこと。
栗の葉は結構固く葉脈も太いため、虫の大きさからするとかなりの力が必要だと思うが、子孫を残すには労力を厭わないらしい。産みつけられた卵が孵って幼虫になると、揺りかごの中の巻かれた葉を食べて成長する。一匹の幼虫を育てるために、その子専用の個室を作るという贅沢な子育て方法は、少子化になると過保護になりがちな人間のよう。
ヤマツツジの枝にぶら下がるコガタスズメバチの巣。トックリを逆さにした特徴ある形は、巣内の保温と外敵の侵入防止のため。これは初期の巣で、女王バチが一匹で作ったもの。この後、女王バチは働きバチを生んで育てるが、働き蜂が羽化するとトックリの先を囓りとって球状になり、まわりにどんどん材料を貼り付け大きな巣に仕上げる。スズメバチは肉食なので、巣に蜜を蓄えることはない。スズメバチといえば恐怖の対象だが、コガタスズメバチは比較的おとなしく、樹を揺らしたり刺激を与えなければ襲ってくることはない。触らぬ蜂に祟りなし。
真っ赤な落ち葉を見つけた。去年のものにしては、あまりにもキレイなので上を見上げたら一枝だけ紅葉している。まだ6月でこれから緑が深くなる季節に紅葉が始まるなんて、よほど気が早いモミジなのだろう。ノムラカエデやイロハモミジなら春から紅いが、青々とした樹の一枝だけの紅葉とは珍しい。何が原因なのだろう。
そんなモミジの花の季節が終わり、プロペラ型の実がついた。竹とんぼのような羽の付いたモミジの種は、秋になると真ん中から半分に折れ、風に乗って遠くへ飛んで行く。
今が盛りの「手まり潅木」。
雨が降らない限り、ほとんど毎日午後は山荘で山仕事に精を出している。計画的に作業をするわけでもなく思いついたところから手をつけるのだが、草刈りにとどまらず混み合っている雑木を切り払い、古い樹でも長生きできるように手入れをしている。
都会派のメイは連れて行っても、すぐに帰りたがるので置いていくが、自然派のララは嬉しそうに何処でも散策している。私が草刈り機やチェンソーを使っているときは近づいてこないが、作業を止めるとどこからともなく近くに寄ってくる。


 赤くないフキ=青ブキではあるが、なかでも上物のフキは、茎の色が薄いグリーンで、まるでマスカットのような色をしている。このようなフキを見つけたら、中フキを残し外フキを採る。中フキとは株の中心で断面が丸く一番太く立派に見える部分だが、そこは切らずに左右の細い部分(外フキ)を採る。外フキは根元の断面が半円形や三日月形の茎で、切り取ると水が流れ出る。1株から2本以上採らないのがマナー。このため、釜を使わずハサミを使う。中フキを採らずに外フキを採るのは、全く味が違うからである。中フキはスジが多く実がペタペタと柔らかい。一方、外フキは香りが良く食感がシャリシャリしていて美味しい。
赤くないフキ=青ブキではあるが、なかでも上物のフキは、茎の色が薄いグリーンで、まるでマスカットのような色をしている。このようなフキを見つけたら、中フキを残し外フキを採る。中フキとは株の中心で断面が丸く一番太く立派に見える部分だが、そこは切らずに左右の細い部分(外フキ)を採る。外フキは根元の断面が半円形や三日月形の茎で、切り取ると水が流れ出る。1株から2本以上採らないのがマナー。このため、釜を使わずハサミを使う。中フキを採らずに外フキを採るのは、全く味が違うからである。中フキはスジが多く実がペタペタと柔らかい。一方、外フキは香りが良く食感がシャリシャリしていて美味しい。