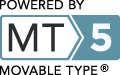こんな古い作家ばかりで、今の人にはわからないだろうなぁ。
オリジナル(ZENA)
湯上がりの濡れた肢体をそっとおくと、彼女の足のウラから秘部にかけて甘い戦慄がかけぬけた。
川端 康成
風呂場の檜の戸を開けると脱衣所であった。部屋が湯気で白くなった。夜の帳に鳴く梟の声が止まった。向う側の座席から娘が立って来て、島村の前のガラス窓を落とした。雪の冷気が流れこんだ。もうそんな寒さかと島村は外を眺めながら、床に敷かれた毛氈の上へ足を一歩踏み出すと、寒々とした感触が闇に呑まれた。
横溝 正史
金田一耕助のすすめで、私がこれから記述しようとするこの恐ろしい物語は、昭和十*年*月*日、浴室の扉が開いたところから始まった。事件の舞台となったこの村には湯*温泉という名で知られる湯治場があり、保養客を集めるのがこの辺りの村々の主ななりわいの道であった。浴室の扉が開けられたのは、夜八時ごろのことだった。私は、緋色の毛氈が敷きつめられている脱衣所に足を下ろした途端、つめたい戦慄が背筋をつらぬいて走るのを禁じえなかった。おお、それがこのまがまがしい事件の発端になろうとは、まだだれも気がついていなかったのである。
星 新一
バスルームの扉を開けると、そこは脱衣所の筈だった。しかし、エヌ氏が、そこに見たものは、おどろいたことに宇宙空間のひずみの中にフワフワとただよう緑色のバスマットだった。エヌ氏は一歩その上に足を乗り出す。異次元へ吸い込まれるような感触が体の中心部へかけて走った。
五木 寛之
金髪の娘がドアを開けて、浴室から出ようとした。充分に熟れた彼女の胸が、ジュンの目の前にあった。まっ白な肌と、甘酸っぱい匂い。ジュンが手をかして濃い葡萄酒色のバスマットの上へ立たせる。「スパシーボ」と、彼女が囁く。額に深くかぶさった金色の前髪の下から、ライラックの花のような素晴らしい色の目がうるんだようにのぞいている。ジュンが外を眺めると、白夜の季節を過ぎた空は黒くビロードのようで、温泉の浴場らしい赤煉瓦の建物が山裾に散らばっていた。(あの山の向うにモスクワがある)と、ジュンは思った。
川上 宗薫
浮気してやろうか、と長江は思った。そして浴室のドアを開けた。長江がバスマットの上に足を下ろすと、目の前に若い女が坐っていた。長江は彼女を憶えている。そのチロチロとした感触を左手の指が憶えていた。裸になれば、見事な胸を持っているらしいことが、長江にはわかっていた。彼女は絶頂の感覚を知っているに違いない。こんな女を腕の中で抱きしめれば、さぞ抱き心地がいいだろうと想像を廻らしていると、女は立ってガラス窓を開けた。窓に手をかけるために爪先でのびあがったので、ミニスカートから豊なふとももが食み出して、長江の欲望を湧きたたせる。窓から雪が吹き込んだ。急な冷気のために鼻腔の奥が痒い感じを起こし、長江はクサメをこらえた。こんな時、彼の官能はきまって刺激されるのだった。長江は女のスカートに手を差し入れようとした。女の体がピクッとなった。そして「いや」といったが、女も昂ぶっていることを、長江は見てとっていた。
宇野 鴻一郎
お風呂からあがったら、とっても気持ちよかったんです。あたし、エロチックな気持ちになってしまった。これは内緒なんだけど、お風呂に入るたんびに感じちゃうみたい。お風呂がいけないんです。お風呂に入ると、あたしいけないことを連想しちゃうんです。ああ、だれか逞しい男が入ってきてほしいなんて思ったりして。ドアをあけて、ピンクのバスマットに足をのせると、その柔らかい感触があたしの指先にからんだからだけど、ピクンと感じちゃったんです。もう立っていられなくて、その場にしゃがみこんじゃったんです。
 「違いがわかる男」のリストに名前のなかった「田村正和」が最近、「ビールと間違いましたー」と叫ぶ「麦とホップ」。発泡酒か第3のビールか知らんけど、それはナイッテ。ゼッタイ間違いませんって。
「違いがわかる男」のリストに名前のなかった「田村正和」が最近、「ビールと間違いましたー」と叫ぶ「麦とホップ」。発泡酒か第3のビールか知らんけど、それはナイッテ。ゼッタイ間違いませんって。 それにしても最近、お気に入りだった「アサヒのプレミアム熟選」、どこにも売ってませんねえ。あまりの旨さに誰かが買い占めてしまったのだろうか。それとも不人気で製造中止になってしまったのだろうか。今となっては私にとって「幻のビール」になってしまった。ま、酔ってしまえば、「違いのわからない男」になってしまうのだが。
それにしても最近、お気に入りだった「アサヒのプレミアム熟選」、どこにも売ってませんねえ。あまりの旨さに誰かが買い占めてしまったのだろうか。それとも不人気で製造中止になってしまったのだろうか。今となっては私にとって「幻のビール」になってしまった。ま、酔ってしまえば、「違いのわからない男」になってしまうのだが。
 ところで、ウチの金魚には皆、名前がついている。出目金は「クロ」、大きなコメットは「コメ」、小さなコメットは「コメッコ」、普通の金魚は「フツウノ」という。エサのときに名前を呼ぶと水面に集まってパクパクする。
ところで、ウチの金魚には皆、名前がついている。出目金は「クロ」、大きなコメットは「コメ」、小さなコメットは「コメッコ」、普通の金魚は「フツウノ」という。エサのときに名前を呼ぶと水面に集まってパクパクする。 もうこうなったらオトコの意地だもんね。新しいブルカミア8kgを購入しなおし、底面フィルターをシリコンでコーキング。いっさいの隙間も許さんぞ。というくらい厳重にリセット。はあー、大変だあ。「俺は、いったい何をやってるんだろ」状態。
もうこうなったらオトコの意地だもんね。新しいブルカミア8kgを購入しなおし、底面フィルターをシリコンでコーキング。いっさいの隙間も許さんぞ。というくらい厳重にリセット。はあー、大変だあ。「俺は、いったい何をやってるんだろ」状態。 子供の頃から、我が家で一番のご馳走といえば「釣りキンキを蒸したもの」だった。大きな皿に1匹丸まんまを乗せ、蒸し器で蒸しただけのもの。これが一人に1匹づつあたるのだから、なんとも贅沢な気分にさせてくれる料理だ。なんたって「釣りキンキ」。今、買うと大きなもので1匹5千円は下らないだろうが、昔でも安くはなかったろう。だからこそ「今夜は蒸しキンキ!」とオフクロが言うと「おーっ!」と歓声が上がったものだ。
子供の頃から、我が家で一番のご馳走といえば「釣りキンキを蒸したもの」だった。大きな皿に1匹丸まんまを乗せ、蒸し器で蒸しただけのもの。これが一人に1匹づつあたるのだから、なんとも贅沢な気分にさせてくれる料理だ。なんたって「釣りキンキ」。今、買うと大きなもので1匹5千円は下らないだろうが、昔でも安くはなかったろう。だからこそ「今夜は蒸しキンキ!」とオフクロが言うと「おーっ!」と歓声が上がったものだ。 我が家では、素焼きの焙烙(ほうろく)で煎茶を焙じて飲んでいる。炒りたてのほうじ茶の香りは、やはり格別。焙煎にかかる時間は、ほんの数分なので、毎回飲む直前に焙じている。そのときの気分によって、浅く煎ったり深く煎ったり。そのとき、部屋中に昔のお茶屋さんの前を通りかかった時のような香ばしい匂いが漂い、いっときの幸せを感じる。
我が家では、素焼きの焙烙(ほうろく)で煎茶を焙じて飲んでいる。炒りたてのほうじ茶の香りは、やはり格別。焙煎にかかる時間は、ほんの数分なので、毎回飲む直前に焙じている。そのときの気分によって、浅く煎ったり深く煎ったり。そのとき、部屋中に昔のお茶屋さんの前を通りかかった時のような香ばしい匂いが漂い、いっときの幸せを感じる。 じつは私、毎日でも「うな重」「うな丼」が食べたい。世の中にこんな旨いものがあるかしら。と思えるくらい大好き。そのうえ、どういう訳か、鰻を食べると、その日一日、精神的に落ち着く。ユッタリとした気分になり、とても優しい気持ちになるから不思議だ。きっとウナギに含まれるナニかの成分が、そうさせるのかもしれない。嘘か誠か試してみたい人は、ぜひ、私に「うな重の松」をご馳走してみてくれませんか。
じつは私、毎日でも「うな重」「うな丼」が食べたい。世の中にこんな旨いものがあるかしら。と思えるくらい大好き。そのうえ、どういう訳か、鰻を食べると、その日一日、精神的に落ち着く。ユッタリとした気分になり、とても優しい気持ちになるから不思議だ。きっとウナギに含まれるナニかの成分が、そうさせるのかもしれない。嘘か誠か試してみたい人は、ぜひ、私に「うな重の松」をご馳走してみてくれませんか。